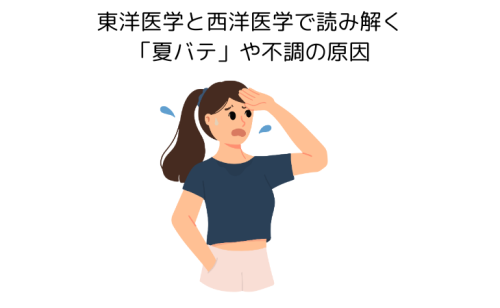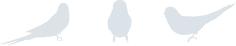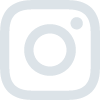Serenite
コラム
2025-07-09 10:47:00
東洋医学と西洋医学で読み解く「夏バテ」や不調の原因
こんにちは。連日猛暑が続いていますが、体調はいかがでしょうか?
この時期、「なんとなくだるい」「食欲がない」「頭がぼーっとする」など、心身の不調を感じる方が多くなります。これはいわゆる「夏バテ」と呼ばれる状態。
では、なぜ夏にこのような不調が起こるのでしょうか?
今回は、東洋医学と西洋医学の視点からその理由を見てみましょう。
【西洋医学の視点】——体温調節と自律神経の乱れ
1. 自律神経の乱れ
暑い日には体温調節のために交感神経が活発になりがちです。
この交感神経が長時間優位になると、副交感神経とのバランスが崩れ、以下のような不調が現れます。
-
倦怠感
-
睡眠の質の低下
-
食欲不振
-
イライラや不安感
また、冷房の効いた室内と炎天下の屋外を行き来することで、急激な温度差が体にストレスを与えます。
2. 脱水と電解質バランスの乱れ
汗を大量にかくことで体内の水分とともにナトリウムやカリウムなどのミネラルも失われます。
これが脱水や熱中症だけでなく、頭痛・筋肉のけいれん・疲労感といった不調につながります。
【東洋医学の視点】——「暑邪」と「気」「脾」の関係
1. 暑邪(しょじゃ)の影響
東洋医学では、夏に影響を及ぼす邪気を「暑邪(しょじゃ)」と呼びます。
暑邪は「陽邪(ようじゃ)」の一種で、強い熱性と上昇性をもち、体の「気」を消耗させやすい特徴があります。
そのため、以下のような症状が出やすくなります。
-
汗をかきすぎて気虚(ききょ)状態になり、だるさや疲労感
-
熱が上昇して頭痛・めまい
-
口渇・不眠
2. 「脾」の働きの低下
夏は冷たい飲み物や食べ物をとる機会が増えるため、東洋医学で消化吸収を司る「脾(ひ)」が冷やされやすくなります。
脾が弱ると、「気」や「血(けつ)」の生成がうまくいかず、食欲不振・腹部の張り・下痢などの消化器系の不調が起こります。
【まとめ】暑さに負けない身体づくりのヒント
| 不調 | 西洋医学的要因 | 東洋医学的要因 |
|---|---|---|
| 倦怠感 | 自律神経の乱れ、脱水 | 気虚、暑邪の影響 |
| 食欲不振 | 暑さによる消化機能低下 | 脾の弱り、冷飲食の過多 |
| めまい・頭痛 | 水分・電解質不足 | 気の上昇、熱の停滞 |
| 不眠 | 自律神経の乱れ | 心火(しんか)の過剰 |