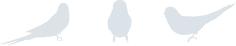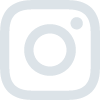Serenite
コラム
“体の土台”から整える理由~施術の考え方について~
~セレニテの施術の考え方について~
「その時は楽になるけれど、また同じ不調を繰り返してしまう」
そんな経験をお持ちの方は少なくありません。首肩こりや頭痛、慢性的な疲れなどの症状は、つらい場所だけをケアしても、体の根本的なバランスが整っていないと戻りやすいのが現実です。
セレニテでは、不調が出ている部分だけでなく、体の土台から整えることを大切にしています。体はすべてつながっており、首肩のこりの背景に、冷えや血流の低下、呼吸の浅さ、内臓の疲れ、自律神経の乱れなどが影響していることも少なくありません。
そのため施術の前にはカウンセリングを丁寧に行い、現在の症状だけでなく、睡眠の状態やストレスの影響、生活リズム、女性ホルモンの変化なども含めて体の全体像を見ていきます。そしてその方に今必要な施術を組み立てていきます。
特に意識しているのが、自律神経のバランスを整えることです。忙しさや緊張が続くと、体は無意識のうちに力が入り、血流が落ち、コリや痛みが出やすくなります。鍼灸で巡りを整え、呼吸が深まり、力が抜けやすい状態へ導くことで、体が本来持っている回復力が働きやすくなります。
セレニテの施術は、強い刺激で無理に変化を出すのではなく、その方の体質や状態に合わせて刺激量を調整しながら、体が自然に整っていくことを目指しています。
「首肩が楽になっただけでなく、体全体が軽い」
「呼吸が深くなり、気持ちまで落ち着いた」
「眠りの質が変わった」
そんな変化を感じていただけるのは、症状だけでなく体の土台から整えているからです。
つらさを繰り返さないために、体全体のバランスを見直すこと。
それが、セレニテが大切にしている施術の考え方です。
大寒の冷えによる不調に|冷え性・自律神経の乱れを整える鍼灸施術
昨日から二十四節気の「大寒(だいかん)」の時期です。
一年で最も寒さが厳しくなる季節で、最近「急に冷え込んで体調が悪い」「肩こりや頭痛が増えた」と感じる方が増えてきます。
大寒は、冷え性や自律神経の乱れが表れやすい時期です。
この記事では、寒さによる不調の原因と、鍼灸でできること、さらに自宅でできる冷え対策(ツボ・温活)をご紹介します。
大寒の時期に増える不調とは?
大寒の頃に増える代表的な不調は以下です。
- 首肩こり(首が回らない・肩が重い)
- 頭痛(こめかみ・後頭部の重さ)
- 腰痛・関節痛(冷えると痛む)
- 手足の冷え・むくみ
- 眠りが浅い/夜中に目が覚める
- 胃腸の不調(食欲低下・下痢・便秘)
- 気分の落ち込み・イライラ
「毎年この時期しんどい」という方は、寒さに体が影響を受けやすい状態になっているかもしれません。
なぜ寒いと体調が悪くなる?冷えと自律神経の関係
冷えで血流が落ちる
寒い環境では、体は体温を守るため血管を収縮させます。
すると血流が低下し、筋肉が硬くなりやすくなります。
その結果、首肩こり・腰痛・関節痛・頭痛につながりやすくなります。
自律神経が緊張しやすくなる
冷えは自律神経にも影響します。
寒さや気温差は交感神経(がんばる神経)を刺激し、体を緊張モードにしてしまいます。
- 寝ても疲れが取れない
- 呼吸が浅い
- 夜中に目が覚める
- いつも力が入っている
こうした状態が続くと、冬の不調が慢性化しやすくなります。
冷え性・冬の不調に鍼灸ができること
鍼灸は、冷えで落ちた巡りを整え、筋肉の緊張をゆるめながら、自律神経のバランスを調整していく施術です。
Sereniteでは以下の点を丁寧に確認し、刺激量を一人ひとりに合わせて調整しながら施術を行っています。
- その方の体質
- その日の冷えの状態
- 緊張の強さ(呼吸・首肩・背中)
- 睡眠の質、ストレス状態
施術後にいただくお声としては、
「体がじんわり温かくなった」「呼吸が深くなった」「頭が軽い」「夜ぐっすり眠れた」など、冷えと自律神経の両面で変化を感じる方が多いです。
冷えにおすすめのツボ3選(自宅で簡単)
セルフケアとして、冷えにおすすめのツボを紹介します。
“強く押す”よりも「気持ちいい強さでゆっくり」がポイントです。
1)三陰交(さんいんこう)【冷え・むくみ・女性の不調に】
内くるぶしから指4本上、すねの骨の内側。
冷え性・むくみ・生理トラブルにもよく使われます。
2)足三里(あしさんり)【体力・胃腸・巡りに】
膝の下、指4本分下の外側。
体を底上げするツボで、冬の疲れやすさにもおすすめ。
3)関元(かんげん)【お腹の冷えに】
おへそから指4本分下。
お腹が冷えやすい方、疲れが取れない方に◎
自宅でできる温活|寒い日におすすめの冷え対策
冷え対策は「温める場所」がポイントです。特に大寒は、次の温活がおすすめです。
①「3つの首」を温める
- 首
- 手首
- 足首
マフラー、レッグウォーマーなどで冷気を遮断するだけで体感が変わります。
② 湯船に浸かる(10〜15分)
ぬるめのお湯でゆっくり。深呼吸しながら入浴すると、自律神経が整いやすくなります。
③ 仙骨(お尻の上)を温める
カイロ・ホットパックが◎
仙骨まわりを温めると、全身が緩みやすく巡りも上がります。
④ 白湯・スープで内側から温める
冷たい飲み物が続くと内臓が冷え、疲れが抜けにくくなります。無理せずできることから試してみてくださいね。
大寒の冷え不調は放置しないのがコツ
大寒の不調は、放っておくと春先まで持ち越しやすいのが特徴です。
「毎年この時期つらい」「冷えが抜けない」「眠りが浅い」という方は、体からのサインかもしれません。
鍼灸サロンSereniteでは、冬の冷え・首肩こり・頭痛・自律神経の乱れなど、季節の変化による不調を丁寧に整えていきます。
無理せず、体の声に合わせたケアを取り入れていきましょう。
朝起きた時の「食いしばり・頭痛・首肩こり」…その原因と鍼灸でできること
「首肩がガチガチで疲れが抜けない」
「寝ている間に歯を食いしばっている気がする」
こうしたお悩みでご来店される方はとても多いです。
実はこの症状、単に“コリ”の問題だけではなく、自律神経の緊張や睡眠の質、ストレス反応が重なって起きていることが少なくありません。
なぜ朝に症状が出るの?
睡眠中、本来は副交感神経が優位になり、筋肉や脳が休まる時間です。
しかしストレスや緊張が続いていると、寝ている間も交感神経(がんばる神経)が働きやすくなり、無意識に力が抜けなくなります。
その結果…
- 顎(咬筋・側頭筋)が緊張 → 食いしばり
- 首・肩まわりが緊張 → 首肩こり
- 後頭部〜側頭部の筋緊張や血流低下 → 頭痛
- 呼吸が浅くなる → 眠りが浅く疲れが取れない
という悪循環が起こりやすくなります。
さらに、スマホやPCで目を酷使している方は、眼精疲労から側頭筋が硬くなり、食いしばり・頭痛につながっているケースも多いです。
鍼灸ではどうアプローチする?
鍼灸の良いところは、局所のこりだけでなく、自律神経のバランスと巡りを同時に整えられることです。
セレニテでは、
- 咬筋・側頭筋・顎まわりの緊張
- 首肩(特に後頭部・首の付け根)のこわばり
- 呼吸の浅さ・胸の緊張
- 頭の疲れ(脳疲労)
- 眠りの質の低下
こういった状態を見立てて、その方に応じた刺激量の鍼でゆるめながら整えていきます。
施術後に
「頭が静かになった」
「呼吸が深くなった」
「朝の顎の疲れが減った」
と感じる方も多く、“緊張のスイッチが切り替わる”感覚が得られやすいのも特徴です。
Sereniteができること
セレニテが大切にしているのは、“今ある痛みを取る”だけではなく、食いしばりが起きにくい体の状態へ整えていくことです。
- ストレスや疲労がたまりやすい方
- がんばり屋さんで緊張が抜けにくい方
- 寝ても回復しにくい方
- 頭痛や肩こりが慢性化している方
こうした方が、少しずつ「力を抜ける」ように体が変わっていくよう、施術と日常のケアを含めてサポートしていきます。
最後に
朝からつらい症状があると、一日がしんどく感じてしまいますよね。
でもそれは、体が弱いわけでも、気合いが足りないわけでもありません。
体がずっと頑張り続けてしまっているサインかもしれません。
無理に耐え続けず、ぜひ一度体を整えにいらしてくださいね。
※強い痛み・しびれ・発熱・急な症状悪化がある場合は、医療機関の受診もあわせてご検討くださいね。
なぜSerenite(セレニテ)の施術は、心まで軽くなるのでしょう?
皆さま、こんにちは。 鍼灸サロン Serenite(セレニテ)です。
「マッサージに行っても、その時しか楽にならない」 「病院に行くほどではないけれど、いつもどこかが不調……」 そんなお悩みを持って、私たちのサロンを訪ねてくださる方がたくさんいらっしゃいます。
今日は、Sereniteが大切にしている「施術の特徴」についてお話しさせていただきます。
1. 「脳疲労」と「自律神経」へのアプローチ
現代の女性は、仕事に家事に、常にフル回転。気づかないうちに「脳」が疲れ、自律神経が乱れてしまっています。 Sereniteでは、単に筋肉をほぐすだけでなく、東洋医学の知恵を用いて自律神経のスイッチを「休息モード」へと切り替えます。 「いつの間にか眠ってしまった」「頭の中の霧が晴れたよう」というお声を多くいただくのは、脳の疲れから解放されるからです。
2. あなただけの「オーダーメイド」な時間
お身体の状態は、季節やストレス、年齢とともに毎日変化します。 だからこそ私たちは、決まりきったルーティンではなく、その日のあなたに合わせた施術を組み立てます。 丁寧なカウンセリングを通じて、その時の心身の緊張を解きほぐす、最適なツボを見極めていきます。
3. 10年後を見据えた「土台作り」
一時的なリフレッシュで終わらせないのがSereniteのスタイルです。 鍼灸によって内側の「巡り」を整えることは、5年後、10年後の自分へのプレゼント。 健やかで日々調子の良い状態が当たり前になると、自然と表情まで明るく、美しく変わっていきます。
お帰りになる際の皆さまの、「なんかスッキリしましたー!」という笑顔。 その瞬間のために、私たちは日々心を込めてお一人おひとりと向き合っています。
毎日を頑張るあなたに、静かな「余白」の時間を。 今週も、皆さまが健やかに過ごせますように。
新しい年の始まりは、体の声を聞くところから。 〜心も体も「ご機嫌」な一年を〜
新しい年の始まりは、体の声を聞くところから。 〜心も体も「ご機嫌」な一年を〜
皆さま、いかがお過ごしでしょうか。 鍼灸サロン Serenite(セレニテ)の岡です。
新しい年が明けると、つい「あれもこれも頑張らなきゃ」と力が入りがちですが、今年は何よりまず、あなた自身の**「心と体がご機嫌でいられること」**を一番大切にしてみませんか?
そのために必要なのが、今、この瞬間の「体の声」に耳を傾けることです。
年末年始、休めたつもりでも、意外とお体には疲れが溜まっているものです。
-
朝、起きた時に「あ、軽いな」と思えていますか?
-
深い呼吸が、お腹まで届いていますか?
-
鏡を見たとき、自然な笑顔になれていますか?
もし、どこかに違和感や重さを感じていたら、それは体からの大切なお便りです。 「今は少し、ゆるめてほしいな」 そんな声に気づいてあげるだけで、体も、そして心もふっと緩み始めます。
Sereniteが目指しているのは、ただ不調を取り除くことではありません。 鍼で全身を整えることで、滞っていたエネルギーが巡り出し、内側からポカポカと温かくなっていく。 その心地よさの先に、「今日もいい感じ」と思えるご機嫌な私が待っています。
「10年後も、今より健やかに、ご機嫌な私でいられるように」
今の小さなサインを大切にすることが、心豊かな毎日への一番の近道です。 もし、自分の声を聞くのが少し難しいな、と感じるときは、ぜひ私たちにそのお手伝いをさせてくださいね。
本年も、あなたが一番心地よく輝けるよう、心を込めてサポートさせていただきます。